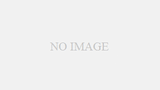どうも、とあるメーカーで研究職をやっているみつこです。
普段、色々な人の話を聞いていると、「あいつは要領がいい」「あのやり方はズルだ」といった発言が散見されます。
作業を効率化するという点ではどちらも同じですが、その内容は大きく異なります。
感情的に使用されることが多い言葉ですが、意味の違いを理解せず、なんでも「要領がいい」「ズル」と断定して話をすると、軋轢を生む可能性があります。
このページでは、これらの違いについて説明していきます。
「要領がいい」と「ズル」の違い
「要領がいい」と「ズル」の違いですが、「ルールに従っているか」がポイントになります。
例えば、計算問題を解く時、手計算ではなく計算機を使用して素早く解答したら「要領がいい」と言えるでしょう。
しかし、計算機の持ち込みが禁止されているテストで、こっそり計算機を使って計算問題を解いたら、それは「ズル」となります。
このように、ルールの中で効率的に作業を行っているのかが大きな違いです。
まとめると以下のようになります。
要領がいい
効率を重視しつつ、正当な手段で物事を進める能力のこと。
要領がいい人 → 周囲の状況を把握し、最適な方法で作業を進める人
具体的には以下の通りです。
①優先順位を明確にする:仕事の中でも特に重要なものを見極め、無駄な作業を減らす。
②仕事を工夫して効率化する:既存の作業手順を見直し、不要な作業の削減やより良い方法を取り入れる。
③周囲と協力する:一人で仕事を抱えず、他者を巻き込んで仕事を円滑に進める。
例:定型業務を自動化し、人が行う作業を削減する。
過去に使用した資料を蓄積し、新しい資料を作成する際に流用する。
ズル
不正な方法で利益を得ようとする行為。
ズルをしている人 → 周囲の状況を利用し、不正な手段で自分だけが得しようとする人
具体的には以下の通りです。
①ルールを無視する:禁止されている抜け穴を利用して利益を得る。
②他者を利用する:仕事の責任を押し付けたり、他者の仕事の手柄を横取りする。
③失敗を隠す:都合の悪い情報を隠し、自分が損をしないようにする。
例:テストでカンニングを行い、高得点を得ようとする。
資料の数値を自分の都合がいいように書き換える。
ルールに従っていれば必ず正しいのか
「ルールに従うことが正しいのか」と言われれば、それは当然だと思うでしょう。
ルールを守ることは重要ですが、機械的に適用するだけでは、他者の反感を買い、逆に非効率となる可能性があります。
例えば、繁忙期に周りが忙しく仕事をしている中、「定時退社がルール」だと言ってすぐに帰宅したり、「有給は権利」といって休んでしまうと、反感を買って全体の士気を下げ、自身も今後の仕事がやりにくくなる可能性があります。
それらの行動自体は間違いではありません。しかし、結果的に効率を下げてしまっては本末転倒です。
そのため、極めて面倒ですが、ルールと周囲の人の感情のバランスを取ることが重要となります。
ルールと人の感情のバランスを取るには
ルールを守りながら周囲の人の感情のバランスを取り、本当に要領がいいと見られるには、次のことを気にするといいでしょう。
①コミュニケーションを取る:自身の仕事を終えることが最優先ですが、周囲の意見も聞き、可能な範囲で手伝いましょう。
②相手の立場を考える:立場によって仕事内容・量が異なります。不用意に相手を煽るような発言は控えましょう。
③自分への期待を理解する:周りが忙しく帰りづらい環境でも、何もせずに待ち呆けていると余計な顰蹙を買う恐れがあります。自分がどのような仕事を求められているのか考え、行動しましょう。
仕事は一人で行うものではなく、数多くの人との関わりの中で進めていくものです。無論、自分とは合わない人はいますが、ある程度は柔軟に対応すべきです。
周りに気を遣うということで余計な気苦労が増え、短期的には損をしていると感じるかもしれません。しかし、他者と良好な関係を築き、チームワークを高めることは、長期的には自身の評価を高めることに繋がります。
まとめ
「要領がいい」と「ズル」の違いは、ルールを守った上で効率的に作業を行っているのかがポイントになります。
単純にルールを守っていても、周囲の感情を無視するとかえって効率を低下させる可能性があります。
そのため、周囲の感情やチームの雰囲気を考慮し、周囲との信頼関係を築きつつ効率的に仕事を進める人が真の意味で「要領がいい人」になります。